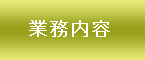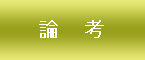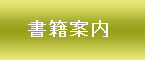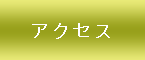消費者契約法は万能か
「不退去」・「監禁」 による「困惑一「困惑」による契約の取消
消費者契約法成立の背景には、事業者と消費者の間にあらゆる面での著しい能力格差が存在し、この格差につけこむことで不当な利益をむさぼり、多数の消費者被害を生み出す悪質事業者が後を絶たないという現代社会の特徴がみてとれる。勧誘時における交渉力にもまた、事業者・消費者間には圧倒的な力関係が成立しており、契約締結を勧誘するにあたって事業者が消費者の住居や勤務先から退去しなかったり(事例Ⅰ)、一定の場所から消費者を退去させなかったりして(事例Ⅱ)契約を締結させるケースが多々みられるものである。このような事業者側の不適切な働きかけが原因となり消費者が自ら欲しない意思表示をなすに至った場合、両者の意思が合致しているとはいえず契約の効力が否定されることが妥当であるといえよう。
消費者契約法四条三項では、契約締結過程において事業者側に「不退去」・「監禁」行為があり、かつこれらの行為が原因で精神的に自由な判断ができない状態に陥ったり、おそれおののいた状態で(法ではこれらを「困惑」と表現する)消費者が意思表示をしたりした場合、意思表示をなした消費者に当該契約の取消権を与えることで消費者の自由意思が尊重されるよう規定されている。
事例Ⅰ
夜八時頃、学習教材の販売員が突然自宅に訪れ、小学校六年生になる息子の成績アップのためにと、教材の内容についての説明を延々と聞かされました。「いらないから帰ってほしい」と何度も断ったのですが、販売員はその都度、説明する商品を替えたり「何で必要ないんだ?」と居直ったりしてまったく帰ろうとせず、結局一二時過ぎまで勧誘行為は続きました。長時間の交渉に頭も朦朧となってしまった私は、早く帰ってもらいたいとの思いもあり不必要ながらも契約してしまいました。
事例Ⅱ
呉服の販売員をしている友人から展示会の誘いを受け、興味半分で行ってみることにしました。会場に入るといきなり数人の販売員に取り囲まれ、誘い文句を次々と浴びせられました。最初は「見るだけのつもりですから」とその場を取り繕っていたのですが、勧誘行為はあまりに執拗に続くため買わずにそのまま帰るのが怖くなってしまい、またたく間に契約させられてしまいました。
二「不退去」・「監禁」行為
法がいう「不退去」行為とは、消費者の住居・勤務地を訪れて契約の勧誘を始めた事業者が、消費者から「帰ってくれ」「時間がありません」「お断りします」等の退去を求める意思を表示されたにもかかわらず、依然としてその場を去らずに勧誘行為を続けることをいう。なおここにいう意思表示は、社会通念上「退去すべき旨を示した」と考えられるものならば、身振り手振りで「契約しないよ」「帰ってくれ」等のしぐさをするような間接的表示であっても構わないとされる。消費者の真の意思が事業者側に明確に伝わってさえいれば、直接的な表示をなした消費者と同様の保護がなされるべきと考えられるからである。事例Ⅰの訪問販売員は「いらないから帰ってほしい」との告知をされたにもかかわらず教材の説明を続けており、明らかな不退去行為に該当するものである。
また「監禁」行為とは、契約の勧誘を受けている消費者が「帰ります」「他の用事があります」「要りません」等の意思を、不退去同様、直接的・間接的に表示したにもかかわらず、事業者がその場から消費者を解放しない行為をいう。事例Ⅱのような展示会商法だけでなく、キャッチセールス・アポイントメントセールスなどの被害も多くが監禁行為に基因している。事例Ⅱのような物理的方法による監禁のほか、「購入しないと不幸が訪れる」などといった心理的方法による監禁も取消しの対象となる。
なお不退去・監禁行為は共に時間の長短を問うものではないので、事例Ⅱのように監禁行為を受けてからまたたく間に交わされた契約であっても取消しが可能となる。
三 尋問の克服
ところで、消費者契約法では立証責任については特別の規定を設けていない。よって事例Ⅰ・事例Ⅱ共に、消費者が訴訟の場で契約取消を実現化するには、原則どおり権利を主張する立場にある消費者側において、事業者の「不退去・監禁行為」と消費者が「困惑して契約を締結した」ことの間に因果関係があることを立証しなければならない。ところが先述のとおり、契約両当事者間におけるあらゆる面での能力格差は消費者契約の特徴であり、このことは紛争解決の場面において、事業者側への証拠偏在という弊害をもたらすことにもなる。消費者側で準備できる直接証拠は極めて限定されるのであり、間接事実の積み上げという困難な立証活動を強いられることになろう。依頼者との面談を通じて、「不退去」であれば訪問の時間帯、訪問者の人相や格好、勧誘の口調、高齢者の独居世帯や母子家庭への訪問など、「監禁」であれば勧誘を受けた場所、事業者の人数や態度、消費者の年齢などといった間接事実を綿密に吸い上げることで契約時の状況を浮き彫りにすることと共に、勧誘時の様子を証言できる者や同種事件の被害者など、立証に協力してもらえる者の調査も必要となろう。そして何より、これら間接証拠を有効活用するための尋問技術の研究・習得が、消費者トラブル解決のための不可欠な要素になると考える。
本人訴訟における尋問(当事者・証人)は、本人へのレクチャーという点で我々司法書士が最も頭を悩ます点である。しかし、ここを突破しないことには消費者契約法が被害救済に対し無力と化してしまうおそれが高い。昨年来、司法書士への簡裁代理権付与の話題が各種紙面を賑わせている。代理権獲得が多少なりとも尋問の克服に役立つことは確かであろうが、器を与えられればそれですべてが解決されるような簡単な問題ではもちろんないわけである。支援型・代理型を問わず、不慣れな尋問をいかに克服し消費者に有利な立証活動を進行できるかが、今後の我々司法書士界における最大の課題となるのではなかろうか。
四「生きた」法へ
困惑取消を実現化するには、消費者の挙証義務は確かに大きな足かせとなる。しかし、「消費者契約の適正化」は本法の精神であり、「不適正な契約に基づいた消費者被害は撲滅されるべき」との考えは、立法過程においてもあらゆる場面で論議されているしその必要性もPIO―NET等の被害報告を検証すれば明白なものとなる。行政サービスの現場において必要視されてきた消費者保護の精神・理念は、様々な紆余曲折があったものの「消費者契約法」として立法化されるに至った。今後、法の精神・理念が司法の場へと受け継がれてることにより、はじめて消費者の真に自由な経済活動が保証されることになるのである。
消費者の被害実態を司法の場へ訴えかけること、証拠偏在の訴訟において立証の問題を克服することは、市民に役立つ法律家を自認する我々司法書士が担うべき使命である。消費者契約法が「生きた法」になるか否かは、消費者の身近に存在する我々の姿勢いかんであるといっても過言ではなかろう。