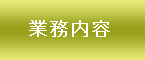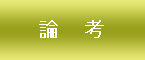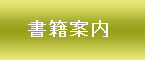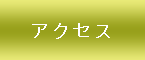行為規制違反と私法上の効果
1 はじめに
改正特商法・改正割販法では、新たな民事ルールの創設に注目が集まっているが、一方で、行為規制の整備も拡充された。本稿は、消費者被害救済の現場に身を置く実務家としての観点から、両法を通じた行為規制に注目し、業者による行為規制違反行為に対する私法上の責任追及の可能性を模索するものである。
2 改正法が定める行為規制
改正法で新設あるいは拡充された主な行為規制を俯瞰すると〔表〕のとおりとなる。各規制の詳細については、日司連編『ここがポイント!改正特商法・割販法』(民事法研究会)を参照されたい。
〔表〕改正法における行為規制
特定商取引法 |
割賦販売法 |
訪販 勧誘を受ける意思の確認義務(3の2Ⅰ) |
包括 個別 支払可能見込額の調査義務(30の2,35の3の3) |
これらの内、割賦販売法の定める適正与信義務は、過量販売解除権(割販35の3の12)や不実告知・事実不告知によるクレジット契約の取消権(割販35の3の13ほか)と、書面交付義務はクレジット契約のクーリング・オフ(割販35の3の10ほか)とそれぞれ対応しているから、購入者は民事ルールの主張をすることにより、適正与信義務違反あるいは書面交付義務違反をしたクレジット会社に対する私法上の責任追及を行うことができる。
それ以外の各行為規制違反に対しては、監督官庁による行政処分や刑事罰の規定が設けられているが、対応する民事ルールは存在しない。このため、被害救済という観点からは「使い勝手が悪い」「実効性が乏しい」等の指摘も少なくない。
3 行為規制に注目する意義
行為規制違反行為が、直ちに民事上の効力に影響を与えないとするのが判例の原則的な考え方だが(最判昭和50年3月6日ほか多数)、行為規制違反行為を信義則上の義務違反と認定して不法行為責任を認めた事案や、行為規制違反行為が公序良俗違反に該当するとして契約無効・不当利得返還を認めた事案も少なくない。後に分析するが、債務者からの取引履歴開示請求に応じない貸金業者に対し不法行為責任を認めた事案(最判平成17年7月19日)は、その代表例である。
このように、行為規制違反行為が、公序良俗や信義則といった一般規定の根拠事実に該当すると評価される場合、それが直ちに民事ルールに違反しない場合であっても、不当利得あるいは不法行為の法理によって被害回復を図る可能性がある。ことに悪質商法被害では、被害回復を図ろうとするときには既に相手方会社が倒産していたり、あるいは会社に見るべき資産がなかったりするケースも少なくないが、このようなケースでは、会社に対する不法行為責任にあわせて、違法行為を承知で業務執行に携わった代表者らに対し、民法709条・会社法429条等を根拠とする共同不法行為責任を追及することによる被害回復手段も検討できる。
また、悪質商法被害では、支払手段としてクレジットを利用しているケースが多い。改正割販法では、クレジット契約に関する複数の民事ルールが創設されたことで、クレジット会社に対する既払金返還請求が可能となる場面は増えたが、民事ルールの適用できない場面では、改正前と同様に抗弁の接続(割販30の4,35の3の19)による未払金の支払停止を主張できるにすぎない。ことに、今回の改正によって創設された民事ルールはいずれも個別信用購入あっせんを適用対象としているところ、すでに悪質業者の多くが、抜本的改正の見送られた包括信用購入あっせんによるクレジット契約へと切り替え済みであるため、実務上は、クレジット会社に対し既払金返還請求のできる場面はさほど多くないように予測される。このため、クレジット会社の行為規制違反を理由に不法行為責任を追及する必要性は、依然として高い。
さらに、民事ルールによる被害回復では、不当利得や原状回復の法理により既払金の範囲内での被害回復が限度となるが、不法行為責任を追及する場合には、実損害に加え、司法書士費用の請求や、悪質性が著しい場合には慰謝料の請求を検討することも可能となる。
以上のような観点から、行為規制に注目する意義は大きい。
4 判例分析
ところで、現実に被害回復を実現するめには、行為規制違反という事実にどのような事情が加味されることで、公序良俗違反や不法行為を構成することになるのかが重要となる。以下、実務における被害回復の観点から、業者の不法行為責任を認めたいくつかの判例分析を試みたい。
(1)貸金業者による取引履歴不開示
前掲・平成17年最判は、金融庁事務ガイドライン(現在は、貸金業法19条の2)を根拠として貸金業者に対し全取引履歴の開示請求を行った債務者が、開示に応じない貸金業者を相手に不法行為責任を追及した事案である。
本件において検討を要するのは、貸金業者の「開示しない」行為、すなわち不作為が、不法行為責任を負うべき加害行為と評価し得るか否かという点だ。
ところで、一般に、社会において人は自由に行動する権利を有する。「行動する自由」の中には「行動しない自由」が含まれているから、行動しないこと(=不作為)が不法行為責任を負うべき加害行為と評価されるためには、作為義務の存在が必要であると解される。さらにこの作為義務は、「行動しない自由」の保障という観点から道義的義務では足らず、法的作為義務の存在が要求されると説明される。
明文上の法的作為義務としては、親権者の監護義務(民820)、扶養義務(民877)等が例示でき、これらの義務に反して監護や扶養を怠り相手方に損害を負わせた者は、不作為不法行為責任を免れない。このほか法的作為義務には、慣習や条理に基づく場合も考えられるが、「行動しない自由」の保障との関係上、作為義務の認定には慎重を要すると説明されている(吉村良一『不法行為法〔第2版〕』有斐閣)。
本件で最高裁は、ガイドラインという行政通達上の作為義務を根拠に、貸金業者の不開示を信義則違反と認定し、不法行為に基づく損害賠償責任を肯定しているが、慎重を要すると解される作為義務の根拠としては、一見すると弱いようにも感じられよう。この点は追って詳述する。
(2)未公開株商法
株式取引を業として行うためには、金融商品取引法(改正前の証券取引法)に規定される金融商品取引業者としての登録が義務付けられているが(金商29)、無登録業者が、未上場あるいは店頭公開されていない株式を売買契約の目的物とし、「上場間近だ」「確実に値上がりする」等のセールストークで顧客を勧誘する手口が未公開株商法の典型である。
未公開株をめぐる現時点の判例の到達点は、「無登録業者によるグリーンシート銘柄(※)以外の未公開株株式の売買は、それ自体極めて違法性が高く、公序良俗に反する違法な取引であるとするのが相当」と判示するものであり(東京地判平成19年12月13日)、未公開株商法であることが、直ちに私法上違法と評価されている。
なお、無登録での営業は刑罰罰の対象でもある(金商198)。
※ グリーンシート銘柄 :日本証券業協会が、①発行会社の法令遵守状況を含む社会性、適時開示体制の整備状況、財務諸表または連結財務諸表に係る公認会計士または監査法人の監査報告書において重要な注記がないこと等、②事業計画に収益性・成長性が認められること等、を考慮し指定する優良な未公開株式のこと。
以下では、未公開株商法をめぐる3件の判例を判旨部分のみ簡潔に採り上げ、裁判実務が前掲・平成19年東京地判へ到達した変遷を分析する。
(2)-① 京都地判平成18年12月1日
10か月にわたり、2社の未公開株を対象とし、12回の売買契約(代金総額3080万円)を締結させた事案。
裁判所は、無登録業者による未公開株商法である事実に加え、業者による「ヘラクレスに上場することになった」「上場株数は2500株だけで希少性がある」等の虚偽説明を顧客が真実と誤信した事実、誤信によって時価をはるかに上回る価格で購入させられた事実、同種の契約が短期間のうちに多数回繰り返されている事実等を認定し、不法行為責任を認めた。
不法行為責任の根拠としては、業者の欺罔行為や、欺罔行為によって顧客が錯誤に陥っていることにつき業者に認識がなかったとは言えない点が中心となっている。
(2)-② 名古屋地判平成19年10月25日
3か月にわたり、1社の未公開株を対象とし、3回の売買契約(代金総額480万円)を締結させた事案。
裁判所は、京都地判同様に業者の虚偽説明等を事実認定したほか、契約の目的物が未公開株である事実、業者が無登録で営業していた事実も認定し、業者による行為規制違反行為をも根拠として不法行為責任を認めた。
(2)-③ 東京地判平成19年11月30日
3か月にわたり、5社の未公開株を対象とし、6回の売買契約(代金総額2220万円)を締結させた事案。
裁判所は、無登録業者による株式の販売である事実、取引の対象がグリーンシート銘柄でない未公開株である事実、結果的に5社のうち1社を除いて上場されなかった事実、経営状態に関する適切な情報開示のない会社の株式は証券取引業の対象とすべきではないとされている事実等を認定し、不法行為責任を認めた。
前2例と比較し、行為規制違反行為を違法性の主要な根拠としている点に注目できる。
(3)「違法性」の判断
ふたつのケースは、いずれも行為規制違反行為に基づく民事上の不法行為責任を認めた事案である。双方のケースでは、どのような事情の下で民事上の責任追及が認められたのだろうか。
(3)-① 判例・学説の整理
判例分析の前に、不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実の内、違法性(権利侵害)について整理したい。
古い判例では「すでに権利として確立している利益」に対して侵害行為のあった場合に限り、不法行為が成立すると判示するものもあったが(大判大正3年7月4日〔桃中軒雲右衛門事件〕)、その後に「法的保護に値する利益であれば足りる」と変更され(大判大正14年11月28日〔大学湯事件〕)、現在に至っている。具体的な権利の侵害に至らなくても、法規違反や信義則違反によっても違法性は認められるとし、民法709条は違法性の表徴として権利侵害という形態が標識されているに過ぎないとの理由付けによる。
学説もこれを支持したうえで、違法性(権利侵害)の枠組みは「被侵害利益の種類」と「侵害行為の態様」との相関的衡量によって判断すると説明される。例えば、身体や生命に対する侵害の場合は行為そのものが違法と評価されるのに対し、本稿で取り上げる消費者被害に代表されるような財産侵害の場合には、業者の説明・情報提供・交渉経緯等に関する個別具体的な「態様」によって、違法性の有無が評価されることとなるのだ(末川博・我妻栄「相関関係論」)。
(3)-② 「不開示」の違法性
平成18年改正前の貸金業規制法には、過剰与信の防止規定が置かれていたが(旧貸金13)、同規定は訓示規定と考えられており、これに違反した貸金業者に対し損害賠償責任を認めた裁判例はわずかであった(釧路簡判平成6年3月16日ほか)。これに対し、取引履歴不開示に関する前掲・平成17年最判は、同じ改正前の貸金業規制法19条に関する金融庁事務ガイドラインを作為義務の根拠として不法行為責任を認定しており、両者の違いは著しい。
この違いは、相関関係論によって説明できる。すなわち、過剰与信は債務者の財産権に対する侵害と評価できるから、これが違法性を帯びるためには個別具体的な「侵害行為の態様」が主張立証されなければならない。
一方で不開示は、単なる財産権に対する侵害を超えて、借主保護を目的とした強行法規である利息制限法によって守られるべき法益を侵害することとなる。利息制限法に基づく元利充当計算を行うためには、貸金業者による全取引履歴の開示が不可欠だからだ。したがって、仮にその根拠がガイドラインという行政通達にすぎないとしても、強行法規によって守られるべき法益という「被侵害利益の種類」が重視され、違反行為そのものが違法性を帯びるものと結論付けられる。
(3)-③ 未公開株商法における保護法益の変容
一方、未公開株商法についてはどうか。未公開株商法による被害事例が報告され始めたのは平成16年前後であろう。当初は、実在の大手非公開会社の株式を取引対象とし、「近く上場の予定がある」などと架空の計画を説明して顧客を募る手口が主流であったが、次第に、自社株の購入を顧客に勧める手口や、株式発行会社と販売あっせん会社とが共謀して顧客を勧誘する手口等の詐欺的商法が次々と編み出され、これに伴って従来の証券取引法による規制を潜脱する手法も次々と考案され、社会問題化されるようになったものだ。
ところで、もともと証券や先物取引等の分野では、被害金額が高額化する傾向にあることも手伝ってか、他の分野の消費者被害と比較して裁判による被害回復を図るケースが多い。多数の裁判例の積み重ねにより悪質業者の実態が裁判の場で明らかとなっていったことから、説明義務・適合性原則・新規委託者保護義務といった判例上の義務が形成されていた。このため、司法においても投資家保護の精神が浸透していたのである。このような事情もあり、未公開株商法における裁判所の判断も、短期間のうちに購入者をより保護する方向へと進んだのだろう。
前掲の3件の判例で分かるように、詐欺的商法により購入者の財産権を侵害した業者の個別具体的な「態様」を中心に争われた初期の裁判例から、次第に取引そのものの反社会性が暴かれるに連れ、投資家保護を掲げた証券取引法(当時)によって守られる法益への侵害行為へと、未公開株商法に対する評価が変容していったのだ。その結果、業者の個別具体的な「態様」という主観的要素よりもむしろ、行為規制違反行為の事実という客観的要素が、違法性認定のために重視されることになっていった。そしてこのことは、購入者にとっての主張立証の負担軽減という効果をもたらしたのである。
5 改正特商法・割販法ではどうか?
ここまで、実務における被害回復という観点から、行為規制違反に基づく私法上の責任追及手段として、業者に対する不法行為責任追及の可否を検討した。責任追及のためには、「被侵害利益」が単に購入者等の財産権であるのか、それを超えた特別法等によって守られる利益であるのかを検討し、被侵害利益が財産権である場合には、さらに個別具体的な「侵害行為の態様」についての主張立証が求められることが確認された。
これを前提に、本稿のテーマである改正特商法・割販法の定める行為規制に違反した業者に対する私法上の責任追及を、最後に検討したい。
(1)旧法下での裁判例
行為規制違反を理由に業者の民事上の責任を認めた旧法下での裁判例は、クレジット会社の加盟店調査管理義務違反を理由に不法行為責任や債務不履行責任を認めたもの(福岡地判昭和61年9月9日,福岡高判平成元年11月9日,静岡地浜松支判平成17年7月11日ほか)と、次々販売に関しクレジット会社の過剰与信責任を認めたもの(高松高判平成20年1月29日,大阪地判平成20年4月23日)とに大別される(詳細は、小楠展央ほか『悪質商法被害救済の実務』282頁,日弁連消費者問題対策委員会『改正特商法・割販法の解説』235頁(いずれも民事法研究会)を参照)。しかし、業者の責任を認めた裁判例はわずかであり、次々販売に関する判例はいずれも、審議会等の議論を経て改正法案がほぼ具体化された後の判決であり、改正法の影響が色濃い。
旧法下では、加盟店調査管理責任は行政通達にその根拠が明記されているにすぎないし、過剰与信防止義務は努力義務に止まっていた(旧割販38)。また悪質商法被害は、利息制限法における「借主保護」、証券取引法における「投資家保護」と比較すると、「被害者保護」という法益が十分に醸成されているとは言い難い分野である。したがって、先の相関関係論の考え方によれば、個別具体的な「侵害行為の態様」についての主張立証が不法行為成立のために必要不可欠であり、訴訟活動にも多大な苦労を伴っていたことが容易に推測される。
(2)今後の展望
改正割販法では、加盟店調査管理義務が適正与信義務(割販35の3の5,35の3の7)、業務適正化義務(割販30の5の2,35の3の20)という形で明文化された。また、過剰与信防止に関する努力義務も、支払可能見込額の調査義務(割販30の2,35の3の3)と支払可能見込額を超える与信の禁止(割販30の2の2,35の3の4)として具体化された。特に業務適正化義務と過剰与信防止義務は、これからの悪質商法被害救済の中心論点となるであろう包括信用購入あっせんを適用対象とする行為規制であるから、被害救済にあたる実務家としては、条文の趣旨や制定の背景等についての深い理解が求められる。
ほかにも、改正特商法に新設された再勧誘の禁止規定(特商3の2Ⅱ)は、消費者トラブルを未然に防止するという観点で、実務上も極めて重要な行為規制である。
ところで、新たな行為規制が法律に明記されたとしても、旧法下での訴訟活動の苦労が直ちに軽減化されるわけではなく、依然として、業者による違反行為の個別具体的態様が違法性の評価に影響を及ぼすことに変わりはない。しかし、法改正を契機として、次々販売に関するクレジット会社の過剰与信責任を認めた判決が出されたことは事実であり、裁判所が、悪質商法被害に関心を示していることが窺われる。この背景には、法改正運動の過程で、次々販売による被害者の声や、被害の実態、業者の販売マニュアル等がマスコミを通じて広く明らかにされたという事情もあり、世論が司法を後押ししたと指摘することもできよう。
そしてこの点こそ、実務家の重要な役割だ。業者の悪質違法な実態や被害の深刻さを、訴訟活動を通じて裁判所に訴え続けたり、運動を通じて広く社会にアピールしたりすることで、被害救済のための土壌は少しずつ醸成されていくものと考えられる。証券や先物取引等の分野で積み重ねられた判例法理が、投資家保護という強い法益を形成し、これによって業者の違法性の認定に資することとなったように、被害額が比較的少額である悪質商法被害の分野で、私たち司法書士が「被害者保護」という新たな法益を形成すべく活動することが、民事ルールだけでなく、行為規制を含めた改正法全体の十全な活用につながるのではないだろうか。